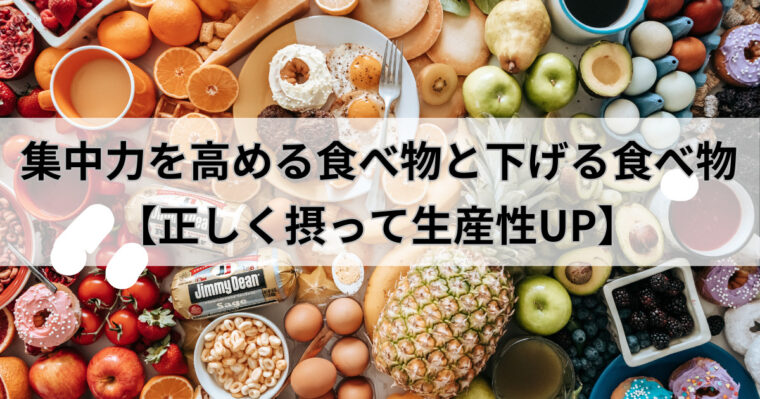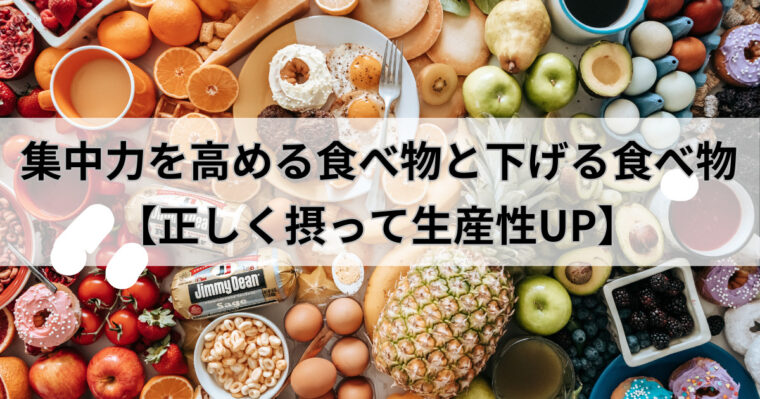職場では仕事に集中できるけど、自宅になると途端に集中できなくなるケースは多いです。
これは、どれだけやる気やモチベーションが高くても同じです。
テレワークや副業が盛んに行われるようになった現在、仕事部屋の需要は高まっています。
かつての私も、テレワークを行うようになってから、
- すぐに気が散る(終わっていない家事が気になる)
- 集中が続かない(娯楽物に興味がそそられる)
- 集中できない(家の中ゆえにダラダラしてしまう)
といったことに悩まされました。
ですが、一念発起し仕事部屋を作ったことで、集中力を飛躍的に高めることに成功しました。
そこでこの記事では、【集中力を高める仕事の部屋の作り方】を解説します。
集中力を高め、仕事で成果を上げたい方は最後まで読んでください。
この記事のピックアップ
- 仕事部屋のメリット
- 仕事部屋のレイアウト例
- 仕事部屋のに必須の要素8選
この記事がオススメな人
- 仕事部屋の作り方が分からない人
- 効果的な仕事部屋を作りたい人
- 仕事で成果を上げたい人
私が実際に作った仕事部屋のポイントを余すことなく記しました。
この記事を読んで、今よりも集中力を高めていきましょう。
仕事部屋のメリット
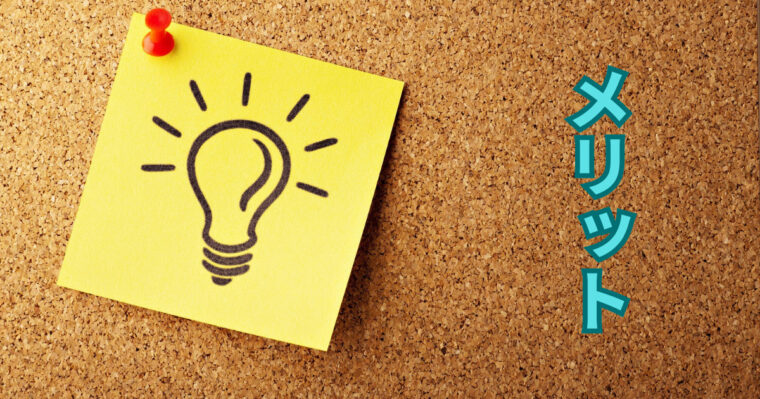
 筆者
筆者仕事部屋の作り方の前に、仕事部屋のメリットについて見ていきましょう。
仕事部屋のメリットは端的に言えば、『仕事の生産性が上がる』ただ一つです。
ですが、生産性が上がる理由について詳しく知ることで、仕事部屋づくりへのモチベーションが高められます。
仕事部屋のメリットは、下記6つ。
- 仕事道具や書類を一カ所にまとめておける
- 娯楽を切り離せる
- 落ち着いて仕事が出来る
- 仕事の書類を置きっぱなしにできる
- 仕事の中断と再開が簡単
- 仕事のルーティン化
これらのメリットが積み重なり合い、仕事の生産性を上げることが出来ます。
集中力を高める仕事部屋のレイアウト【ポイント4個】





ここでは、仕事部屋で絶対に押さえておきたいレイアウトポイントを解説していきます。
仕事部屋を作る際、以下4つのポイントは押さえておきましょう。
- 窓の位置
- 解放感のある空間
- 娯楽物は置かない
- ドアとデスクの位置
それぞれ解説していきます。
窓の位置
仕事部屋を作るなら、窓の位置は利き手の反対にしましょう。
理由は、手元に影が出来るから。
利き手側に窓があると、外からの光によって手元に影ができます。
影が出来ると、手元が見えづらくなり、その分の作業効率が落ちてしまいます。



確かに、字を書いている時に影がチラつくとうっとうしいよね。



そうなんだ。だから、頻繁に字を書く人は注意して欲しいかな。
デスクライトを使えば、ある程度は解消できる。
だけど、一番は利き手の反対側に窓がある状態かな。
- パソコンでしか作業しない
- 影が気にならない
といった方は、特に気にしなくて良いでしょう。
解放感のある空間を意識する
仕事部屋は解放感を意識して作りましょう。
テレワークなどで仕事部屋を使う場合、長い時間同じ部屋にいることになります。
同じ部屋に長時間いると、
- 圧迫感や
- 閉塞感
を感じやすく、『モチベーションの低下』や『集中力の低下』に繋がります。
だからこそ
仕事部屋は解放感を意識し、『圧迫感』や『閉塞感』を感じにくくする必要があるのです。
娯楽を切り離す
仕事部屋には、娯楽に関する物は置かないようにしましょう。
例えば、
- マンガ
- ゲーム
- テレビ
- スマートフォン
など。
これらの物は仕事部屋に置かない方が良いです。
理由は単純で、気が散って仕事に集中できないから。
私たちは、脳の情報の約80%を視覚から得ていると言われています。
よって部屋の中に娯楽物があると、あればあるだけ注意が逸れてしまうのです。
仕事部屋には、
- 仕事道具や
- 仕事の書類
だけを置くようにしましょう。



仕事とプライベートはきっちり分ける感じだね。



仕事部屋には、人が写ったポスターも置かない方が良いです。
人が写っているものは、注意が向きやすく、気が散ってしまいます。
デスクと入口の位置
仕事部屋にデスクを置くのなら、ドアが視界に入る位置に置いてください。
くれぐれも、デスクの後ろ側に入口が来ることは避けましょう。
デスクの後ろ側に入口があると、私たちは無意識化で、
「人が来るんじゃないか」
と気にしてしまいます。
この常に「気になっている」状態が集中力にとって良くありません。
人が来ないかが気になるあまり、集中力が低下するわけです。



入口がデスクの前にあるか、後ろにあるかだけですが、想像以上に変わりますよ。
どこを仕事部屋にするか


先ほど、4つのレイアウトポイントをご紹介しました。
4つのレイアウトポイントに注意して頂ければ、集中力を高める仕事部屋に近づけます。
ですが、4つのポイントだけではまだ足りません。
どこを仕事部屋にするのか考える必要があります。
基本的に仕事部屋を作る場所は
- 間取り
- 部屋数
- 居住人数
によって決まります。
そして多くの場合に選ばれるのが、
- リビング
- 寝室
です。
選ぶ場所が悪いと、仕事部屋を作る意味が無くなります。
『どこに仕事部屋を作れば良いのか?』下記3つの要素から見ていきましょう。
- 間取りと居住人数によって仕事部屋の位置は決まる
- リビングを仕事部屋にする
- 寝室を仕事部屋にする
それぞれ見ていきましょう。
間取りや居住人数によって仕事部屋の位置は決まる
まず前提として、仕事部屋は『仕事をするだけの部屋』にするのが理想です。
例えば、
- リビング
- 寝室
などの部屋と兼用させない方が良いということ。
ですが、多くの場合
- 間取り
- 部屋の数
- 居住人数
などの理由から、一つの部屋を丸々仕事部屋として使うのは難しいです。
仕事部屋を作る前に、
- リビングや寝室と兼用になるのか
- 仕事部屋のみとして使えるのか
考えてみましょう。
リビングを仕事部屋にする場合
リビングを仕事部屋として兼用させる場合、下記メリットとデメリットがあります。
リビングにワークスぺースを設けるのはおすすめしません。
リビングでは、
- 家族が立てる音
- テレビの音
- 家族の談笑
といった音があります。
加えて、邪魔が入ることも多いです。
つまるところリビングで仕事をしても、仕事の生産性は上がりづらいです。
唯一のメリットは、家族との交流が減らないこと。
仕事部屋を作ると、自然に家族との交流時間が減ります。
逆に、リビングにワークスペースを設けることで、家族と接する機会が減りません。
寝室を仕事部屋にする場合
寝室を仕事部屋として兼用させる場合、下記メリットとデメリットがあります。
寝室はリビングによりも、仕事に集中しやすくおすすめです。
寝室にワークスペースを設ければ、朝起きてからすぐに仕事を始めることが出来ます。
ベッドの中でダラダラする時間を減らせます。
加えて、寝室であれば家族が居たとしても、プライベートな空間を保つことが可能。
仕事の邪魔が入りません。
しかし寝室のワークスペースにもデメリットは存在します。
寝室ということは、すぐ近くにはベッドがあるわけです。
すると『ちょっと疲れたし休もうかな』という誘惑に駆られやすく、休みがちになるリスクがあります。
それに、仕事とプライベートの切り替えが難しくなります。
就寝前に少しだけ仕事をするつもりが、何時間も経っていた…といったように、仕事とプライベートのメリハリがつかなくなりかねません。



私は昔、寝室と仕事部屋を兼用させていました。
ですが、『疲れたから』『頑張ったから』など。何かと理由を付けて休んでいたので止めました。
仕事部屋のレイアウト例


仕事部屋のレイアウトはデスクをどこに置くかで決まります。
- 壁際に置くか
- 中央に置くか
- 部屋の角に置くか
など。
デスクの位置によって、仕事部屋を『おしゃれな部屋』にも『機能性に富んだ部屋』にも出来るのです。
ここで紹介するレイアウト例を見て、自分にとってどのような仕事部屋が向いているのか決めていきましょう。
デスクを壁に合わせておくレイアウト




まず初めに紹介するのは、デスクの長辺を壁につけるレイアウト。
このレイアウト方法は最も一般的なものです。
デスクを壁に付けることによって、
- 余計な物が目に入らない
- 壁を有効活用できる(ホワイトボードを掛けたり、資料を貼ったり)
といったメリットが得られます。
しかしメリットだけでなく、デメリットもあります。
デスクの長辺を壁につけるレイアウトでは、目の前に壁があるため、圧迫感を感じてしまうのです。
特に奥行きの浅いデスクは、圧迫感がより顕著に感じられます。
圧迫感がある状態では、集中力が低下すると言われているため、注意しましょう。
デスクを部屋の角に置くレイアウト




デスクを部屋の角に置く場合、良く使われるのがL字型デスクです。
L字型デスクは作業スペースを広くとれるのが魅力。
- デュアルディスプレイ
- プリンター
- ファクシミリ(FAX)
など。仕事に必要な物品を自分好みの位置に置くことが出来ます。
また、部屋の角にデスクを置くことによって、開放的な空間を作り出すことが可能です。
しかしこのL字型デスクの場合も、壁との距離が近く、圧迫感を感じやすくなります。
壁との間にゆとりを持たせるなど、工夫が必要です。
デスクを中央におくレイアウト




最後に紹介するのが、部屋の中央にデスクを置くレイアウト方法です。
このレイアウトは部屋が広い場合におすすめ。
壁との距離が遠くなるので、視界が広く、圧迫感を感じにくいです。
その反面、
- 部屋が狭いと窮屈感が増す
- 部屋が片付いてないと、視界に入ってきて気が散る
- 機器の配線がめんどう
といったデメリットがあります。



私はこのレイアウト方法でデスクを配置しています。
壁から距離をとり、開放的な空間の中仕事に集中できるのが魅力です。
2人部屋の場合のレイアウト方法




2人部屋の場合のレイアウトで、注意するべきは以下の2点です。
- 対面でデスクを置かない
- 同室者と距離をとる配置にする
対面でデスクを置くと、常に同室者が視界に入って仕事に集中できません。
また、横並びでデスクを置いていたとしても、距離が近ければ同じです。
2人部屋の場合は、自分だけのスペースを作ることを心がけましょう。
集中力を高める部屋作りに必須の要素【8選】


ここまで、仕事部屋のレイアウト方法について解説してきました。
紹介したポイントを守ることで、集中力を高める仕事部屋を作れます。
ですが、まだ不十分です。
集中力を高める要素はレイアウト以外にも8個あります。
- 物は必要最低限のものだけを置く
- 騒音・雑音対策を行う
- 身体に合ったデスクと椅子を使う
- アナログ時計を置く
- 光の向きと色に配慮する
- 集中力が高まる香りを見つける
- 集中できる温度と湿度を保つ
- 緑視率を高める
この8個の要素を取り入れることで、更に集中力を高めることが可能になります。
物は必要最低限のものだけを置く
私たちの脳は、約80%のリソースを視覚情報の処理に充てています。
これは目に見えるものからの影響を強く受けることを意味します。
どれだけ高い集中力を維持できる人でも、ふと視界の端にマンガやゲームが入ってしまえば集中力の低下は避けられないでしょう。
また、私たちの気を引くものはマンガやゲームだけに限った話ではありません。
- 雑誌
- 食べ物
- テレビ
など。私たちの意識を乗っ取ろうとするものはたくさんあります。
それらの物の中でも特に危険なのが以下の3つです。
- 食べ物
- 性に関するもの
- スマートフォン
食べ物と性に関するものは私たちの三大欲求に属しており、一瞬目にするだけでも集中力が乱されてしまいます。
スマートフォンにあっては、目の前に置いたりポケットに入れておくだけでも、睡眠不足の時並みに認知能力が低下することがカルフォルニア大学の研究から判明しています。(唯一、認知能力が低下しなかったのはスマートフォンを別の部屋に置いた場合)
仕事部屋には作業に関するものだけを置き、デスクの上には仕事で使うもの以外は置かないようにしましょう。
騒音・雑音対策を行う
どのような場所にいても周りが騒々しければ集中することなんて出来ません。
おそらく、学生時代に以下のような経験をしている人は多いのではないでしょうか。
・図書館で勉強していたら、子どもたちが騒いでいて全く集中することが出来なかった
・家で勉強しようとしたら、道路で工事を行っており、工事音が気になって勉強に集中することが出来なかった
同じ経験をしていなかったとしても、似ている状況に遭遇したことはあるでしょう。そして、周囲がうるさいと集中力を保つことが出来ないことも感覚的に理解していると思います。
この周囲の音によって、私たちの集中力が減衰するという事実は科学的にも証明されています。
ウェールズ大学が行った研究によると、
- 好きな音楽を聴きながら認知テストを行う
- 嫌いな音楽を聴きながら認知テストを行う
- 無音の状態で認知テストを行う
以上の3つのグループでは、無音状態で認知テストを受けたグループが最も成績が良く、他のグループは成績が50%程度落ちていたことが判明しているのです。
騒音・雑音対策における一番の理想は、作業スペースを決める際に静かな場所を選ぶこと。
とはいっても、そんなことが出来るのはごく僅かな人しかいません。
なので、対策方法を2つご紹介します。
- 耳栓をして音をシャットアウトする
- ホワイトノイズマシンを使って音をかき消す
この2つのツールを使えば、騒音対策は簡単に行えます。
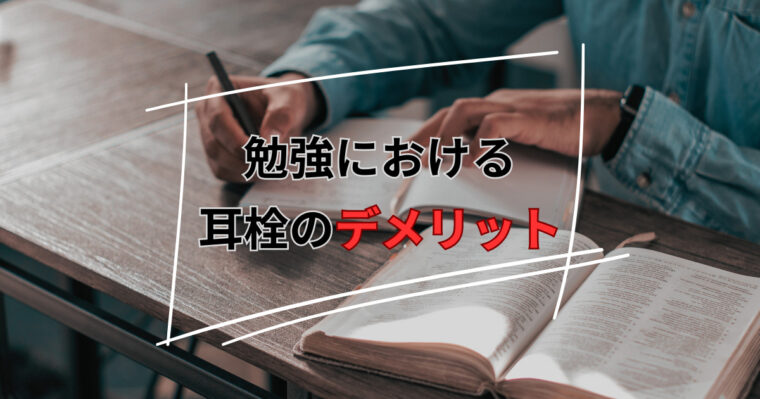
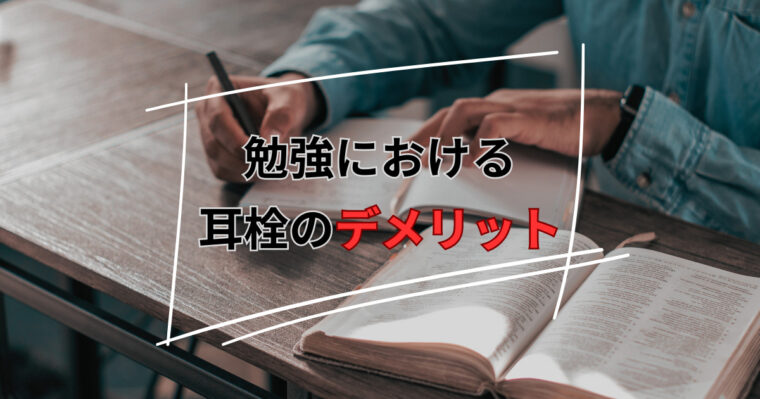
身体に合ったデスクと椅子を使う
椅子とデスクがあっていないことも集中力を削ぐ原因の一つです。
その理由は身体への負担にあります。
椅子と机が合っていないと正しい姿勢を維持することが出来ません。
姿勢が崩れると、身体の一部分への負担が増してしまいます。これが肩こりや腰痛の原因となるのです。
せっかく仕事や勉強に集中することが出来ていたのに、
- 肩が凝ってきたから…
- 腰が痛くなってきたから…
といって集中力を途切れさせたことがある人は多いでしょう。
長時間座っていても肩や腰に負担が掛からないように、椅子と机の高さには配慮する必要があります。
アナログ時計を置く
生産性の低い人が使っている部屋には時計がありません。
では、何で時間を確認しているのかということになりますが、生産性の低い人はスマートフォンで時間を確認しています。
ですが、仕事中はなるべくスマートフォンを使うべきではありません。
理由はスマートフォンは、目の前にあるだけでも私たちの集中力を低下させるから。
時間を確認するたびにスマートフォンを目にしていたら、高い集中力を維持することなんて出来るわけがないのです。
仕事部屋にはアナログ時計を置きましょう。
理由は時間の流れが可視化され、細かく時間を認識できるようになるからです。
アナログ時計は文字盤と長針と短針によって構成されており、針の位置を見れば数字を見なくても感覚的に時間を知ることが出来ます。
もちろん、デジタル時計でも時間を知るという役目を果たすことが可能です。
しかし、デジタル時計では時間経過がぼやけてしまいかねません。
仕事のプロジェクトの締め切りを『2週間後』と大雑把に考えるか『14日後』と細分化して考えるのと同じです。
- 「もうこんな時間か…」
- 「まだこれだけの時間しか経っていない…」
といった経験を誰しもしているように、私たちは時間を把握するのが上手くありません。
アナログ時計であれば時間の流れを可視化してくれるので時間を把握し、どんな作業も効率的にこなすことが出来ます。
光の向きと色に配慮する
仕事部屋は光にもこだわりましょう。
こだわるポイントは以下二つ。
- 光の向き
- 光の種類
光の向き
仕事スペースにおける光源の位置は利き手の反対にしましょう。理由は単純で光源が利き手側にあると、字を書く際などに影が出来てしまうから。
手元が暗いとミスが増えますし、目も無駄に疲れるので気を付けましょう。
光の種類
光には大雑把に分けて3種類あります。
- 白昼色(青が混じった白色)
- 昼光色(白色)
- 電球色(オレンジ色)
この3つの中で仕事スペースに取り入れたい光は『白昼色』です。
青みがかった光である白昼色には、脳を覚醒させる効果があります。白昼色であれば、自分の意思に頼らずとも自然と頭を覚醒し仕事や勉強に集中することが可能です。
仕事部屋やデスクライトで昼光色や電球色を使っており、仕事や勉強に集中できていない人は白昼色に変えてみることをオススメします。
集中力が高まる香りを見つける
私たち人間には、
- 嗅覚
- 聴覚
- 触覚
- 味覚
- 視覚
の『五感』が備わっています。
この五感の一つである『嗅覚』を上手く利用することで、集中力を高めることが可能です。
五感の中でも嗅覚だけは唯一、脳の中枢部位である『大脳辺縁系』に直結しています。
これは嗅覚で得た情報がダイレクトに脳へ伝わるということであり、他の感覚器官の情報よりも早く届き、強く作用することを意味します。
では、私たちに強い影響力を持つ嗅覚でどのようにして集中力を高めるのか?
方法は簡単です。
集中力を高める効果を持つアロマを嗅ぐことで集中力をアップさせることが出来ます。
集中力が高められるアロマは以下の通り。
- ローズマリー
- レモン
- ペパーミント
- スイートオレンジ
- ユーカリ
- レモングラス…など
上記のアロマで集中力を高めることは出来ます。
が、匂いは人によって好みがかなり変わってくるものです。
幾ら集中力を高められるからと言って、不快に感じる匂いの中で作業をしていても意味がありません。
私は過去上記のアロマは全て試しました。
しかしローズマリーとユーカリの匂いが好みでなく、全く作業効率が上がりませんでした。
ですが、それからペパーミントとスイートオレンジの匂いを嗅ぎながら作業に励んだところ、上手く作業効率を上昇させることに成功しています。
私のような例もあるため、「集中力が高められるなら何でもいいや」と投げやりになることなく、自分に合った匂いを探してみてください。
集中できる温度と湿度を保つ
私たちの集中力は温度と湿度によって影響を受けます。これは誰しもが体感して知っていることでしょう。
寒すぎる環境や暑すぎる環境では、仕事や勉強などどのようなことであっても集中することは出来ません。梅雨の時期のジメジメとした環境でも同様のことが言えますね。
では、集中力を高めて生産性をUPさせるような温度と湿度とは何度であるのか?それは以下の通りです。
集中力を高める温度
まず、集中力を高めることが出来る温度は『25度』です。
この25度という数字は2005年にコーネル大学が行った研究結果がもととなっています。
同研究はフロリダの保険会社の従業員を対象に行われたものであり、室温と生産性の関係を調査したもの。結果は下記のとおりです。
1 か月にわたる調査で、オフィスの温度が華氏 68 度から 77 度に上昇すると、タイピング エラーが 44% 減少し、タイピング出力が 150% 跳ね上がりました。
CORNELL CHRONICLE Study links warm offices to fewer typing errors and higher productivity
※”華氏”はアメリカで使われている温度の単位です。(華氏68度は20℃を指し、77度は25℃を指します)
上記のことから私たちにとって集中力を高め、生産性をUPさせる温度は25度だといわれています。
ですが、ここで一つ注意して頂きたいのが、全ての人にとって25度がベストな温度ではないということ。
私たちは個々人によって
- 性別
- 年齢
- 体形
などに違いがあります。これらの違いによってそれぞれが持つ筋肉量や脂肪の量、引いては基礎代謝量が変わってきます。
基礎代謝量が変わるということは、つまり、寒さや暑さの感じやすさが違ってくるということです。
以上の通り、個々人によって適切な温度は変化していくため、25度を目安の温度としてそこから自分に合った温度を見つけていきましょう。
集中力を高める湿度
集中力を高める湿度は40~60%です。
この湿度帯が推奨される理由は、ジメッとした環境かカラッとした環境かによって変わります。
\ジメジメとした高湿度な環境で起こること/
- 体感気温の上昇
-
湿度20%あたり体感温度が約4度上昇すると言われており、集中するのに適切な温度であったとしても、暑く感じてしまう可能性があります。(例、梅雨の時期の蒸し暑さ)
- カビやダニが発生しやすくなる
-
高湿度な環境ではカビやダニが発生しやすくなり、体調を崩す原因となります。また、ジメジメとした空間は不快感を与え集中力を切らせる要因となります。
\カラッとした低湿度な環境で起こること/
- ウイルスが増殖しやすい
-
風邪やインフルエンザのウイルスは湿度が40%の環境下において活発化しやすく、体調を崩す原因となります。
- 目の乾燥を招く
-
乾燥した空間にいると肌や鼻など身体の水分が失われていきます。
特に注意したいのが目の乾燥です。目が乾燥すると、瞬きの回数が増えます。すると、パソコン作業などの目を酷使する作業において大きく効率を低下させることになります。
緑視率を高める
生産性アップには緑視率を高めることも重要です。
緑視率とは、大阪府の緑視率調査ガイドラインでは下記のように定義されています。
緑視率とは、人の視界における草木、すなわち緑の多さを計る割合のことです。
引用:緑視率調査ガイドライン
この緑視率を高めることが生産性アップに繋がる理由は2つあります。
- 集中力が上昇する
- ストレスが軽減される
様々な研究結果から、見える範囲に植物を置くことで集中力が向上し、ストレスが軽減されることが判明しています。
また、やみくもに緑視率を高めれば良いというわけではありません。
コモレビズによると、緑視率の最適解は10~15%とのこと。
緑視率を高めるには観葉植物を置くのが手っ取り早く、多くのサイトでは推奨されています。ですが、緑視率を高めるために観葉植物を購入するのはお勧めしません。
観葉植物は植物なだけあって水やりや土替えなどを行う必要があり、忙しい人にとってはタスクを増やすことになってしまいます。
では、緑視率を高めることを諦めるのかというと、その必要は全くありません。
忙しく、水やりや土替えをしたくない人でも、フェイクグリーンであれば観葉植物を購入せずとも楽に緑視率を高めることが出来ます。
フェイクグリーンとは、いわゆる『造花』のこと。
ニトリやホームセンターなどで手に入れることができます。
フェイクグリーンであれば、水やりや土替えなどの手入れをする必要が無く、簡単に緑視率を高めることが可能です。
ちなみに、下記サイトにて緑視率を計測することが出来ます。
作業が捗るデスクとチェアを紹介


ここからは作業が捗るデスクとチェアを紹介していきます。
生産性を高めるなら『スタンディングデスク』
仕事の生産性を高めるのなら、スタンディングデスクが一番です。
スタンディングデスクには、
- 眠くなりづらい
- フットワークが軽くなる
- 腰痛の改善
- 集中力アップ
など。
メリットが数多くあります。



私もスタンディングデスクを使っています。スタンディングデスクに変えたからは、作業効率が大幅に向上しました。
スタンディングデスクの良いところを知りたい方は下記記事を読んでみてください。


デスク周りをすっきりさせるなら『ラック付きデスク』


ラック付きデスクであれば、デスク周りをスッキリさせることが出来ます。
ラック付きデスクには、
- ラックが前に付いているタイプ
- ラックが後ろに付いているタイプ
の2種類あります。
自分の部屋に合ったタイプを選びましょう。
広々としたデスクなら『L字型のデスク』


L字型のデスクであれば、デスク上を広々と使えます。
- 書類
- ペン
- キーボード
色々な物を置いても気になりません。
また、『片面ではパソコン作業をする』、『もう片面では書き仕事をする』といったようにタスクごとに分けられるのも魅力的です。
スタンディングデスクを使うなら『スタンディングチェア』


スタンディングデスクを仕事部屋で使うのなら、椅子はスタンディングチェアがおすすめです。
スタンディングチェアであれば、スタンディングデスクで立ち疲れた時もすぐに座ることが出来ます。
加えて、『半立位』の姿勢もとれます。
半立位は『立ち姿勢』と『座位姿勢』の中間のような座り方です。両方の姿勢の良いとこ取りをしている姿勢であり、おすすめ。
スタンディングチェアと半立位については下記記事が参考になります。


腰痛対策なら『コイズミのJG5』


『コイズミのJG5シリーズ』は長時間座ることの多い、デスクワーカー向けの椅子です。
腰や背中といった長時間座っていると疲れてくる部位の負担を軽減する構造をしています。
シンクロロッキング機能により、身体の動きに合わせて背もたれと座面が連動。さらに4段階の角度変更が出来ます。



カラーも5色から選べて、自分に合ったものを見つけられるね。
おしゃれさを求めるなら『ヤマソロ Panna』


仕事部屋をおしゃれな空間にしたい!という方には『ヤマソロのPanna』がおすすめ。
カラーバリエーションも豊富で、部屋に合ったものを選びやすいです。
加えて『PUレザー(合成皮革)』を使っているため、手入れも簡単にできます。
【まとめ】仕事部屋づくりは面倒、だけど効果はある
最後にこの記事の重要部分についてまとめます。
仕事部屋のレイアウトを決める際、以下4つの点に注意しましょう。
- 窓の位置は利き手の反対
- 解放感のある空間を意識する
- 娯楽物は置かない
- デスクは入口が見える位置に置く
この四つのポイントは、集中力を高める部屋づくりのベースとなります。
さらに仕事部屋としての機能を高めたい場合は、下記8個の要素が必要です。
- 物は必要最低限のものだけを置く
- 騒音・雑音対策を行う
- 身体に合ったデスクと椅子を使う
- アナログ時計を置く
- 光の向きと色に配慮する
- 集中力が高まる香りを見つける
- 集中できる温度と湿度を保つ
- 緑視率を高める
上記の要素を部屋に組み込むことで、仕事部屋の効果を高めることが出来ます。
また、仕事部屋を作るのなら、
- 家具
- 道具
にもこだわりましょう。
- 自分の体調・体格・性格
- 仕事の種類・方式・頻度
など。
自分や仕事にマッチした道具を使うことで、仕事部屋の生産性を高めることが出来ます。
以上が本記事のまとめです。
正直なところ、仕事部屋づくりは面倒くさいです。
道具をそろえたり、家具を移動させたりなど。
ですが、仕事部屋は絶対に作った方が良いです。
仕事部屋を作れば、仕事に集中できるようになります。集中力が高まれば、仕事で成果を上げることも可能になる。
私がそうでした。
『夢』や『目的』を達成するためにも、ぜひ当記事で紹介していることを実践してみて下さい。



他に仕事部屋づくりに役立つ本とか資料ってないの?



あるよ。
『集中できないのは、部屋のせい。東大卒「収納コンサルタント」が開発!科学的片づけメソッド37』という本がおすすめだよ。
この本には、科学的根拠のある「片付け術」が紹介されています。
『仕事や勉強の集中力を高めること』に特化した方法がまとめられており、仕事部屋づくりの参考になります。



当ブログでは、他にも仕事の生産性を高める方法を紹介しています。
今よりも更に仕事を早くこなしたい方は、ぜひ覗いてみて下さい。
\関連記事/